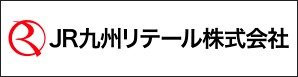一般事業主行動計画
一般事業主行動計画
第二次ウェルビーイング行動計画
~次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画~
2025年3月1日
(4)健康経営の推進
ア 健康経営の推進
目標26
健康経営に取り組み、毎年度の健康経営優良法人の認定を目指すとともに、健康経営に対する社員の評価を高める。
◇取組内容◇
●随時
社長の健康経営を推進するメッセージを、社内ポータルサイトにおける動画配信や各種会議等を活用して発信する。(2023年~)
●2025年11月
会社の健康経営について社員へのアンケートを実施する。(2022年)
●毎年10月
次年度の健康経営優良法人認定の申請を行う。(2023年10月~)
※参考値
会社の健康づくりの取組に対して評価している社員の割合46.3%(2022年度健康意識調査)
イ 健康課題の把握と健康づくりの推進
目標27
社員の健康診断受診率の向上に取り組む。
◇取組対策◇
●毎年8月〜12月
健康診断の実施について社員への周知徹底と脱漏者への個別の受診勧奨により、受診率100%を目指す。
目標28
社員の心身の健康づくりを推進し、肥満傾向にある社員の減少に取り組む。
◇取組内容◇
●2025年3月~
安全衛生委員会等で社員の健康課題や健診結果を共有し、BMI値25以上の肥満傾向にある社員の減少等に必要な取組を検討する。(従来~)
リラックスルームを活用する。(2022年~)
●2025年10月~
社員を対象に健康に関するアンケート調査を実施する。(2022年~)
●毎年5、11月
社内ウォーキングイベントを実施する。(2022年~)
ウ 男女双方の健康に関する理解促進
目標29
男女双方の健康について理解を深め、お互いの健康を気遣う職場風土をつくる。
◇取組内容◇
●2025年5月~
男女双方の健康問題について理解を深めるための研修等を実施する。(2023年~)
健康のために必要な情報提供や利用できる制度の周知を図る。(2022年~)
(5)地域におけるウェルビーイングの促進
ア 地域の子どもたちと子育て世帯の支援
(ア)職場体験の受入れ
目標30
職場見学やインターンシップなど子どもたちや若者の職場体験を受け入れる。
◇取組内容◇
●2023年6月~
子どもたちの職場見学や若者のインターンシップなどを受け入れる。
(イ)子育て世帯の応援と子どもの交流機会の提供
目標31
子育てを応援するサービスの提供や、子どもたちが交流するイベントの実施・協力を行う。
◇取組内容◇
●2025年3月~
KTS「Smile Baby Project はじめてばこ」(赤ちゃんが誕生した家庭へのお祝いボックスのプレゼント)に協賛する。
子どもを対象としたイベントに協賛したり、出店する。(従来~)
「かごしま子育て支援パスポート事業」及び「宮崎県子育て応援サービスの店事業」への店舗登録を促進する。(2023年12月~)
【かごしま子育て支援パスポート事業】
事業に協賛する企業や店舗が、「子育て支援パスポート」を提示した県内に在住する妊娠中の方及び
18歳未満の子どもがいる世帯に割引や独自の優待サービスを提供することで、子育て世帯を応援する鹿児島県の仕組(県と共同実施している鹿児島市の事業名は「にこにこ子育て応援隊支援事業」)
【宮崎県子育て応援サービスの店事業】
事業に協賛する企業や店舗が、「子育て応援カード」を提示した県内に在住する高校生以下の子どもと妊娠中の方のいる家庭に割引や独自のサービスを提供することで、子育て家庭を応援する宮崎県の仕組
(ウ)青少年の見守り
目標32
青少年が健やかに成長する環境づくりのために、コンビニエンスストア・セーフティステーション(SS)活動を推進する。
◇取組内容◇
●2025年3月~
各店舗においてSS活動を展開し、関係機関と連携して地域の子どもたちへの声掛けや見守り、交流機会の提供等を行う。(従来~)
【コンビニエンスストア・セーフティステーション(SS)活動】
(一財)日本フランチャイズチェーン協会に加盟するコンビニエンスストアにおける活動
ⅰ安全・安心なまちづくりに協力
(防犯・防災対策)
①自主防犯(強盗・万引きなどの防止対策)体制の強化
②緊急事態(災害・事件・事故・急病人など)に対する110番・119番通報
(安全対策)
①女性・子どもなどの駆け込みへの対応
②高齢者・身体障がい者の方への買い物のお手伝いと連絡
③認知症が疑われる方の保護と連絡
④地域顧客への安全情報の発信、提供
※警察署・交番、地域包括支援センター、交通安全協会、消防署などとの連携
ⅱ青少年環境の健全化への取組
①20歳未満者への酒類・たばこの販売防止
②18歳未満者への成人向け雑誌の販売・閲覧防止
③青少年非行化(近隣住民の迷惑となるたまり場化、営業の妨害となるたまり場化)防止
④ 体験学習の受け入れ
※警察署、少年サポートセンター、青少年育成団体、学校・ PTAなどとの連携
ⅲ関連事項への取組
①店舗周辺の清掃徹底
② 地域との交流・連携の強化
目標33
子どもたちの安全・安心のため、直営店の「子ども110番の家」、「こども110番・おたすけハウス」の登録を推進する。
◇取組内容◇
●2025年6月~
「子ども110番の家」(鹿児島県内)、「こども110番・おたすけハウス」(宮崎県内)に未登録の直営店舗について、登録申請を進めるとともに、加盟店にも登録申請を働きかける。(2023年10月~)
イ DE&Iとジェンダー平等推進の取組の情報発信
目標34
DE&Iやジェンダー平等推進の取組が地域で広がるように、会社の取組を情報発信する。
◇取組内容◇
●2025年3月~
各機関・団体のDE&Iやジェンダー平等の推進に参考になるように、当社の取組を情報発信する。(2020年~)
ウ 性の多様性の理解促進
目標35
店舗における商品展開等を通じて、社会における性の多様性への理解を深める啓発活動を行う。
◇取組内容◇
●毎年6月
店舗におけるレインボーカラーをあしらった商品等の展開を通じて、性の多様性やLGBTQの理解促進のための啓発を行う。(2021年~)
エ 高齢者等の支援・見守り
目標36
高齢者や障害者の買い物の支援や地域の方の見守りのため、コンビニエンスストア・セーフティステーション(SS)活動を推進する。
◇取組内容◇
●2025年3月~
各店舗において、高齢者や障害者の買い物の支援や地域の方の見守りなどのSS活動を展開する。(従来~)
目標37
認知症サポーターの店舗スタッフを中心に、認知症の方の店舗における買い物支援や見守りを行う。
◇取組内容◇
●2025年3月~
認知症サポーターに養成した社員及び加盟店のオーナー・従業員を中心に、店舗において認知症の方の買い物支援や見守りを行う。(2022年~)
オ スポーツ振興と健康づくりの促進
目標38
地域におけるスポーツや健康に関する活動への協力や参加を通じて、スポーツ振興と健康づくりの促進に取り組む。
◇取組内容◇
●2025年3月~
学校や地域で開催されるスポーツ教室等にアスリートである社員を派遣したり、地域や各社のスポーツや健康づくりの活動に社員が参加・協力する。(2022年~)
(6)計画推進体制の整備
ア 計画推進体制の整備
目標39
計画の進捗管理を行うウェルビーイング推進員を選任し、社内で定期的に計画の進捗状況の検証を行い、計画を計画的・総合的に推進する。
◇取組内容◇
●2025年3月
男女雇用機会均等推進員と職業家庭両立推進員を兼ねるウェルビーイング推進員を選任する。(2023年4月~)
●2025年5月~
部門長会議等で定期的に計画の進捗状況の検証を行う。
【男女雇用機会均等推進員】
職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするため講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者。男女雇用機会均等法により、事業主の選任が努力義務となっている。
【職業家庭両立推進員】
企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭の両立を図るための取組を企画し、周知等の業務を担当する者。育児・介護休業法により、事業主の選任が努力義務となっている。
イ 計画の周知と社員の意見反映
目標40
計画の内容について、社内の周知を図るとともに、社員の意見を反映する。
◇取組内容◇
●2025年5月~
計画について、社員へのアンケート調査を実施する。(2023年4月~)
●2025年4月~
会議や社内ポータルサイト等を活用し、計画の内容及び進捗状況について社内の周知を図る。(2023年3月~)
ウ 関連情報の公表
目標41
会社のホームページと厚生労働省のウェブサイト「女性活躍・両立支援総合サイト」で、計画とその関連情報を公表する。
◇取組内容◇
●2025年3月~
会社のホームページと厚生労働省のウェブサイト「女性活躍・両立支援総合サイト」に、計画とその関連する情報を公表する。(2023年4月~)
【厚生労働省令に基づく情報公表項目】
1「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」区分
①採用した労働者に占める女性労働者の割合
②男女別の採用における競争倍率
③労働者に占める女性労働者の割合
④係長級にある者に占める女性労働者の割合
⑤管理職に占める女性労働者の割合
⑥役員に占める女性の割合
⑦男女別の職種または雇用形態の転換実績
⑧男女別の再雇用または中途採用の実績
⑨男女の賃金の差異
2「職業生活と家庭生活との両立」区分
①男女の平均継続勤務年数の差異
②10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
③男女別の育児休業取得率
④労働者の一月当たりの平均残業時間
⑤雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間
⑥有給休暇取得率
⑦雇用管理区分ごとの有給休暇取得率
※常時雇用労働者301人以上の企業は、1の①~⑧から1項目と⑨の項目、2の①~⑦から1項目の計3項目の情報を公表する必要がある。また、常時雇用労働者が101人以上300人以下の企業は1と2の16項目から1項目以上の情報公表が必要。